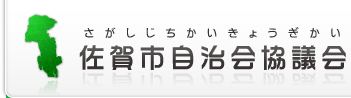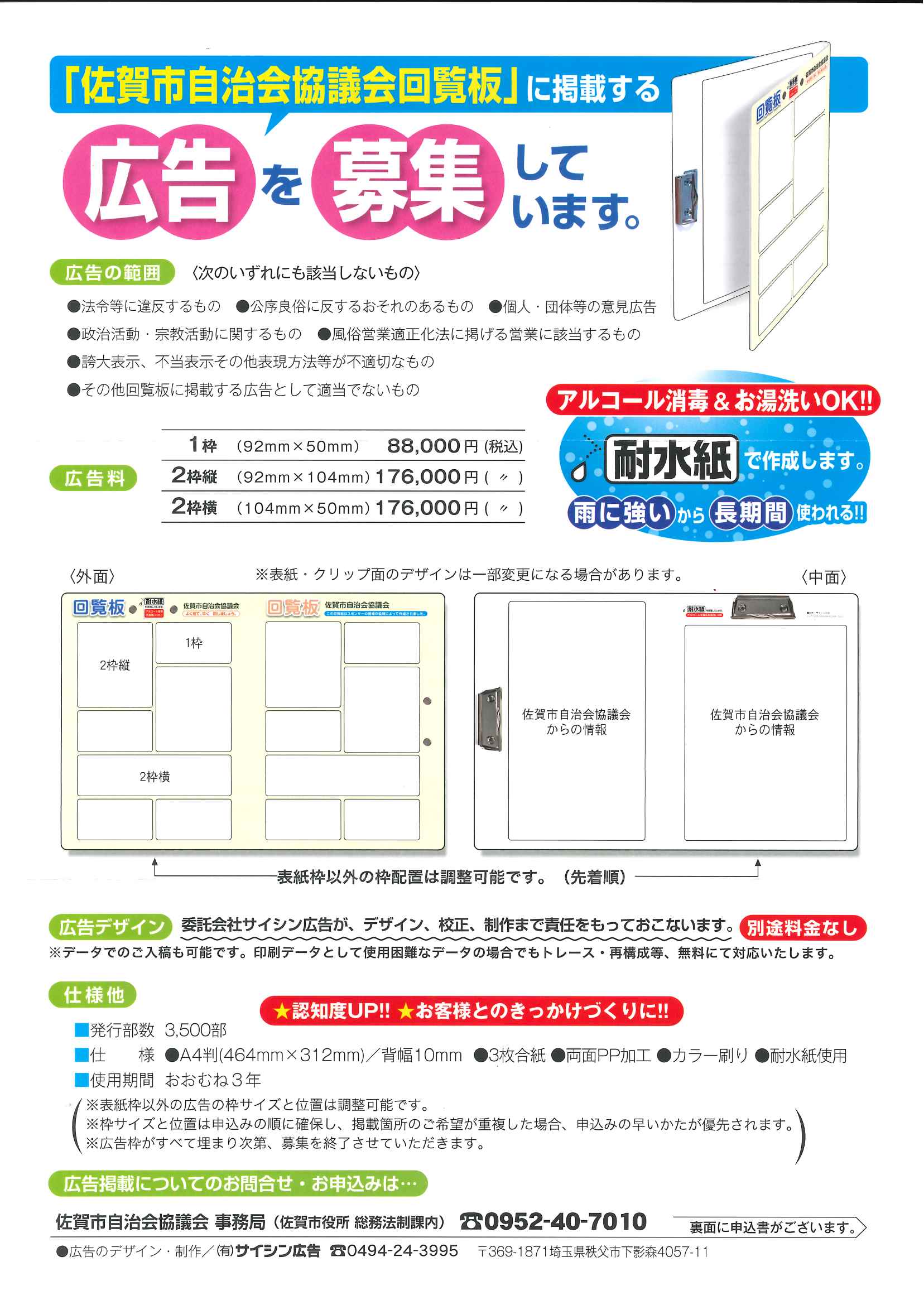2026,01,13, Tuesday
令和7年度自治会長視察研修報告
今年度の自治会長視察研修は、11月20日(木)から21日(金)までの2日間、市内各校区から53名の自治会長が参加し「地域コミュニティ」をテーマに福岡県飯塚市へ行きました。
一日目は一般社団法人家庭教育研究機構みんなのおうち、筑豊地区まちづくり協議会の方から講話をいただきました。
開会の挨拶のあと、一般社団法人家庭教育研究機構みんなのおうちの代表理事から「不登校の児童へのサポートと地域との関わりについて」というテーマでお話しをしていただきました。
子どもを信じて待つ、大人は力を尽くす、そっといなくなる、この3つを心がけて支援を行っていることや、自分と他人の心と体を傷つけないというルールのみを運営側からは課しており、それ以外のルールは児童で話し合って決めているそうです。
活動の一つに休眠預金制度を活用し、不登校の児童に向けて学校の中に居場所を作る校内フリースクール事業を2年半行い、学校関係者と協力して不登校の児童を支えたことを挙げられました。また児童の98%が進学しており、普通科の高校への進学も多いとのことでした。家から出られず支援が届いていない多数の児童に対するケア事業も、取り組みの一つだそうです。




続いて筑豊地区まちづくり協議会事務局長による講話をいただきました。
筑豊地区まちづくり協議会は自治会長会、公民館主事会、青少年健全育成会、各小中学校のPTA等の様々な団体により構成されており、総務、保健福祉、教育、産業観光の4部会があるそうです。
まちづくり協議会は「まちづくり協議会がまちづくりを行っているわけではなく、地域の住民が中心でまちづくりをやっている」という考え方を大事にしているとのことです。
活動を行っていく中で、子育て世帯の困り事などを自治会長にいいづらい、と聞いたことがあり、その意見を吸い上げる目的で「ちゃぶ台会議」を始めたり、中学校長の発案で卒業生にあたる様々な職種の人を招待し、中学1年生と意見交流をする場を設けたりと、地域との関わりを密にしているとのことでした。
また、「みんなのおうち」には夏祭りでブースを出してもらうなど、お互い様の精神でやっていて、この考え方を要として様々な団体が協働してまちづくりを行っているとのことでした。
質疑応答では、どういった理由で不登校になることが多いかと質問に対し、理由は多様であるため本人には聞かず、それよりも今できる学びに注力しているとお答えいただきました。代表理事も自身が不登校になった理由が分かったのは40代になってからでした、ともお話しくださいました。


二日目の、いいかねPallet(株式会社BOOK)の研修は、代表から施設の成り立ちや運営内容などをお話しいただいたあと、施設内の見学を行いました。
代表2名は双方とも猪位金地区出身で、東京で音楽及び映像を制作されており、猪位金小学校が廃校になる際に利活用者の公募に応募するために帰郷。田川市が示す芸術支援施設という活用方法の中でも、音楽家が育つ場所にしたいと思い応募し、現在の運営に至っているそうです。
廃校を活用した施設内には飲食店やギャラリー等があり、更には全国から来た居住者もいるとのことでした。当初、地域の方からは、私たちが何をしているのか分からないという声があり、田川を好きになってほしいという思いを、地域のみなさんに伝えられていなかったことに気づいたそうです。そこで、地域の祭りやイベントに出向く、清掃活動に参加する、また居住者の方々も率先して活動してくれたことが地域との橋渡しになり、地域の方々に施設を利用いただくことも増えていったそうです。
他にも、宿泊事業、イベント企画事業、滞在事業、フリーペーパーや映像を作る事業の4つが施設内に存在しているとのことです。また、地域のためにNPOを立ち上げ、こども食堂やフリースクール(別経営)を廃校内に配置してあるとのことで、代表から施設内を案内していただきました。




今回の研修では、地域での子どもの居場所作りや大人も楽しみながらの地域への関わり方など色々な話を聞くことができ、「地域の繋がり」が大切だということを改めて考える機会となりました。佐賀市にも、新たに移住してこられた方、外国人の方や、様々な活動を行っている方などがいらっしゃいます。この研修を参考に、それぞれの地域の特徴を生かしつつ、つながりを大切にできる地域でありたいと思います。
一日目は一般社団法人家庭教育研究機構みんなのおうち、筑豊地区まちづくり協議会の方から講話をいただきました。
開会の挨拶のあと、一般社団法人家庭教育研究機構みんなのおうちの代表理事から「不登校の児童へのサポートと地域との関わりについて」というテーマでお話しをしていただきました。
子どもを信じて待つ、大人は力を尽くす、そっといなくなる、この3つを心がけて支援を行っていることや、自分と他人の心と体を傷つけないというルールのみを運営側からは課しており、それ以外のルールは児童で話し合って決めているそうです。
活動の一つに休眠預金制度を活用し、不登校の児童に向けて学校の中に居場所を作る校内フリースクール事業を2年半行い、学校関係者と協力して不登校の児童を支えたことを挙げられました。また児童の98%が進学しており、普通科の高校への進学も多いとのことでした。家から出られず支援が届いていない多数の児童に対するケア事業も、取り組みの一つだそうです。




続いて筑豊地区まちづくり協議会事務局長による講話をいただきました。
筑豊地区まちづくり協議会は自治会長会、公民館主事会、青少年健全育成会、各小中学校のPTA等の様々な団体により構成されており、総務、保健福祉、教育、産業観光の4部会があるそうです。
まちづくり協議会は「まちづくり協議会がまちづくりを行っているわけではなく、地域の住民が中心でまちづくりをやっている」という考え方を大事にしているとのことです。
活動を行っていく中で、子育て世帯の困り事などを自治会長にいいづらい、と聞いたことがあり、その意見を吸い上げる目的で「ちゃぶ台会議」を始めたり、中学校長の発案で卒業生にあたる様々な職種の人を招待し、中学1年生と意見交流をする場を設けたりと、地域との関わりを密にしているとのことでした。
また、「みんなのおうち」には夏祭りでブースを出してもらうなど、お互い様の精神でやっていて、この考え方を要として様々な団体が協働してまちづくりを行っているとのことでした。
質疑応答では、どういった理由で不登校になることが多いかと質問に対し、理由は多様であるため本人には聞かず、それよりも今できる学びに注力しているとお答えいただきました。代表理事も自身が不登校になった理由が分かったのは40代になってからでした、ともお話しくださいました。


二日目の、いいかねPallet(株式会社BOOK)の研修は、代表から施設の成り立ちや運営内容などをお話しいただいたあと、施設内の見学を行いました。
代表2名は双方とも猪位金地区出身で、東京で音楽及び映像を制作されており、猪位金小学校が廃校になる際に利活用者の公募に応募するために帰郷。田川市が示す芸術支援施設という活用方法の中でも、音楽家が育つ場所にしたいと思い応募し、現在の運営に至っているそうです。
廃校を活用した施設内には飲食店やギャラリー等があり、更には全国から来た居住者もいるとのことでした。当初、地域の方からは、私たちが何をしているのか分からないという声があり、田川を好きになってほしいという思いを、地域のみなさんに伝えられていなかったことに気づいたそうです。そこで、地域の祭りやイベントに出向く、清掃活動に参加する、また居住者の方々も率先して活動してくれたことが地域との橋渡しになり、地域の方々に施設を利用いただくことも増えていったそうです。
他にも、宿泊事業、イベント企画事業、滞在事業、フリーペーパーや映像を作る事業の4つが施設内に存在しているとのことです。また、地域のためにNPOを立ち上げ、こども食堂やフリースクール(別経営)を廃校内に配置してあるとのことで、代表から施設内を案内していただきました。




今回の研修では、地域での子どもの居場所作りや大人も楽しみながらの地域への関わり方など色々な話を聞くことができ、「地域の繋がり」が大切だということを改めて考える機会となりました。佐賀市にも、新たに移住してこられた方、外国人の方や、様々な活動を行っている方などがいらっしゃいます。この研修を参考に、それぞれの地域の特徴を生かしつつ、つながりを大切にできる地域でありたいと思います。