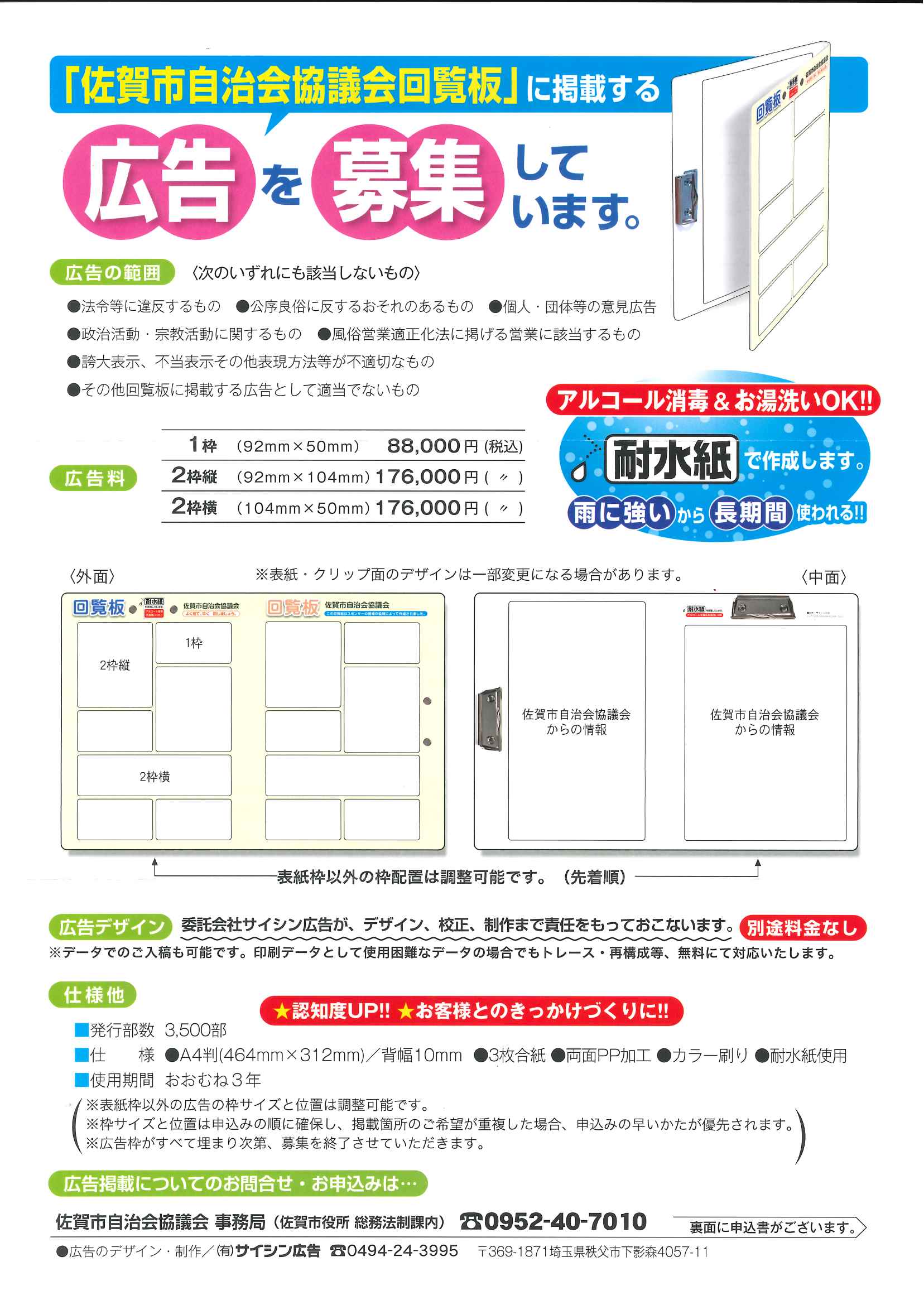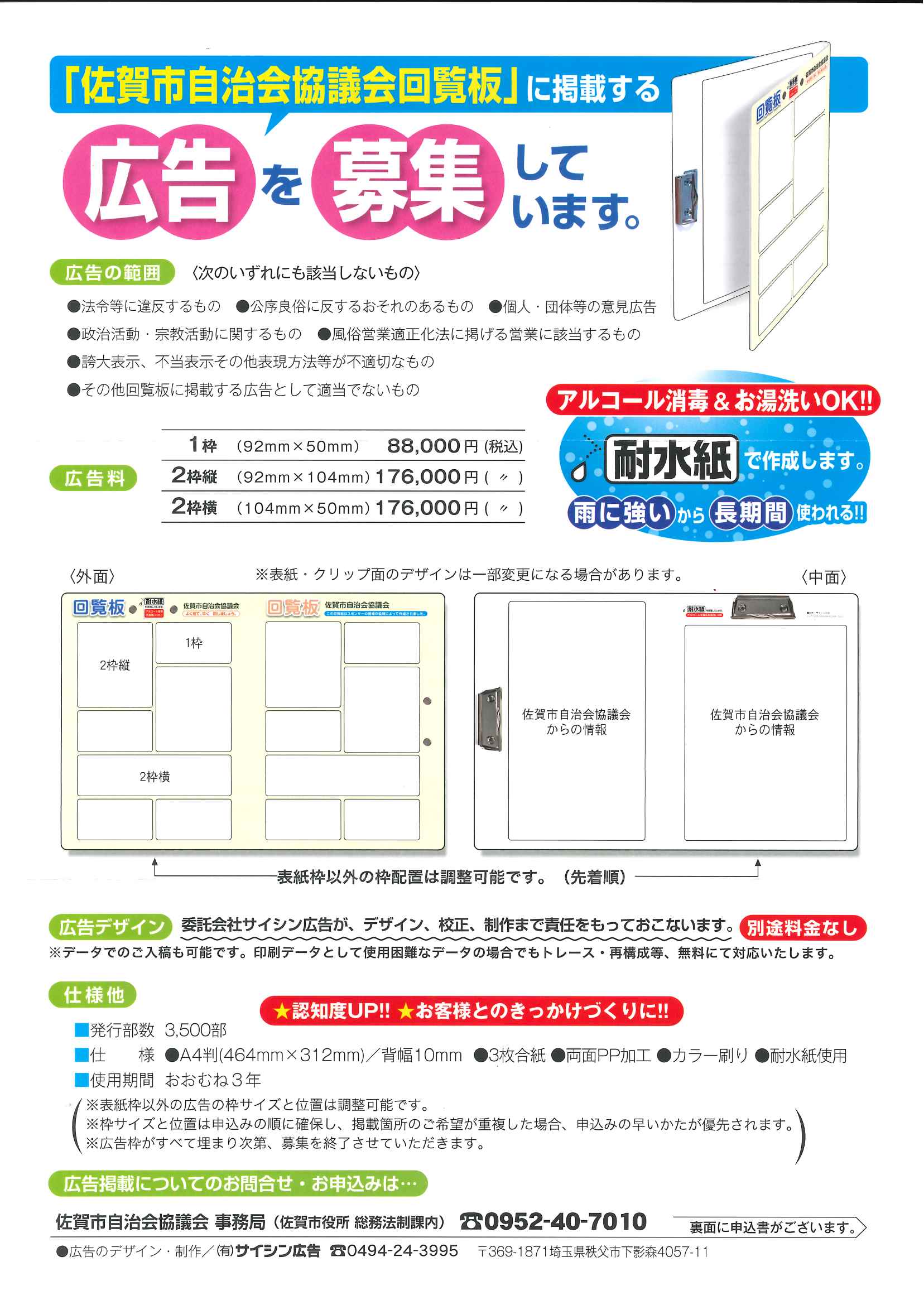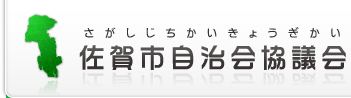今年度の自治会長視察研修は、11月21日(木)から22日(金)までの2日間、市内各校区から54名の自治会長が参加し、「防災活動が活発な自治会等」をテーマに、熊本県益城町にあるNPО法人と区長会の方々にお話しいただきました。


開会の挨拶のあと、NPО法人益城だいすきプロジェクト・きままに、の吉村静代代表から「主役はわたしたち~避難所からのコミュニティ形成~」というテーマで講話をしていただきました。
講話の最初に、「熊本地震からの8年」という7分ほどの動画で当時を振り返りました。その後、吉村代表が経験された避難所4ヶ月、仮設住宅3年間の暮らしなどをお話しくださいました。
吉村代表は震災前から、地域づくりのため、町おこしや自主防災ボランティア活動などを活発にされていました。そのほか、地域づくりボランティアやボランティア連絡協議会、防災ボランティアなどの団体を次々に立ち上げられたということでした。
2016年4月14日、16日の熊本地震発生後、ご自身が避難された避難所の運営を買って出て、まずは避難所内(小学校体育館)の非常口の確保などの区画整理を行い、避難された方へ身の回りの整理整頓・清掃を毎日お願いしていく中で、避難所の中でのコミュニケーションが徐々に生まれたそうです。また、避難所内に子どもや大人が集うコミュニティカフェのスペースを確保したことや、会食コーナーを設けてみんなで会話をしながら食事をしたことで、順調にコミュニティが形成されていったとのことでした。その他にも、避難所の運営は避難者でやれば臨機応変な対応ができること、避難所は生活の場であること、役割分担はあえてしないことなどが大切なことだとお話しくださいました。
4ヶ月の避難所生活を終了し、仮設住宅へ移行したときには、仮設住宅での生活を自立への第一歩と位置付け、避難所で培ったコミュニティを大切にしたことで更なるコミュニティが形成され、それらが自宅再建や災害復興住宅への移行に繋がっていったとのことでした。今現在は、居住地の移動などでばらばらになった仲間たちを繋ぐための活動を続けていらっしゃるそうです。
また、阪神淡路大震災や東日本大震災の被災者の方々から語り継ぐことの大切さを教えてもらい、熊本地震のことを伝えていくための語りべ活動を続け、全国の皆さんへ向けて、防災・減災に繋がれば、という思いで、ご自身の体験等を熊本から発信されているとのことでした。


続いて、益城町区長会の役員の皆さまのご紹介があり、土屋洋一会長から、町の概要や熊本地震についてお話しいただきました。
益城町は5つの校区、68の行政区からなり、空港や物流施設などの充実に加え、熊本市に隣接していることから、ベッドタウンとしても発展。また、30年以内に大地震が来る確率は1%未満だと考えられていたとのことでした。
2回の熊本地震によって、ほぼ全ての住民が避難者となり、避難所は大混乱に陥りました。役場本庁舎自体の被災や、行政職員参集状況の未把握などが、初動対応の遅れに繋がってしまったこと、支援物資が大量に届いたことによる仕分け・配分の難しさなど、避難所の運営改善をはじめ、防災力強化などが急務となりました。
復旧・復興の取組みとして、町民主体のまちづくりへの移行を目指した校区ごとのまちづくり協議会の設立や、避難地(平時は公園)・避難路の整備、また、熊本県と一体となり行っている道路拡幅事業により、安全で快適な道の整備を進めていること、そのほかにも様々な取り組みをしている途中である、とのことでした。




質疑応答の時間には、自主防災組織について、防災訓練の規模や範囲はどれくらいなのか、地震後に一番多かった悩み事は何か、などの質問がなされ、ひとつひとつに丁寧に答えていただきました。区長会の役員の方からは、地震が起きた際のたくさんのアドバイスもいただき、時間を超過する意見交換の場となりました。


最後に、谷川地区にある、国の天然記念物に指定された布田川断層帯を見学しました。同じ場所に方向の違う2つの断層がV字型に地表に表出しており、同一視点からそれらの分岐を確認することができる国内でも稀有な震災遺構について、ガイドの方から説明を受けました。被災した馬小屋など、震災当時のまま残してあるものもあり、地震の規模や影響など、肌で感じることができました。


快く視察を受け入れていただいたNPO法人の皆さま、益城町区長会の皆さま、益城町役場の皆さまに対し、心から感謝いたします。
翌日には、こちらも熊本地震で被災した、阿蘇市の阿蘇神社を訪れました。神社の歴史から震災、復興に至るまでをガイドの方に説明いただきました。
今回の研修では、熊本地震について、避難所からのコミュニティ形成、震災への備えなどを学ぶことができました。佐賀は災害が少ないと慢心することなく、日ごろから防災意識を持ち、地域の方々とのコミュニケーションを取ることは大切なことだと、改めて思えた研修となりました。