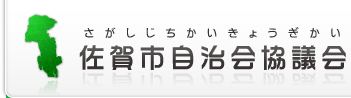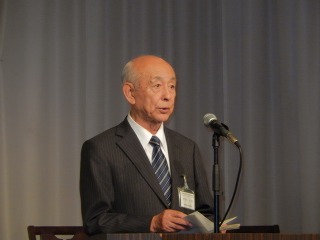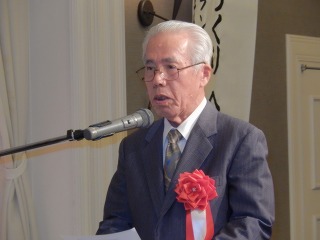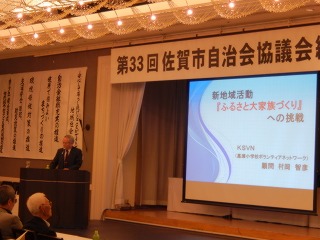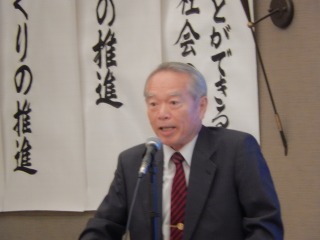自治会長視察研修を11月16日(月)~17日(火)の2日間、今年7月に世界文化遺産に登録された、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産を視察しました。
構成資産は、九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)・山口を中心に全国8県11市に分布して立地していますが、相互に密接な関係があるそうです。
1日目は、熊本県荒尾市にある「三池炭鉱万田坑」へ。
万田坑は、三池炭鉱の20世紀初頭を代表する坑口で、揚炭と入気を目的とした第一竪坑と、人や資材の昇降と排気を目的とした第二竪坑、それらに付随する施設から構成されています。明治35年に開かれ、昭和26年に石炭採掘の役割を終え、その後、平成9年の三池炭鉱の閉山まで主に坑内水の排水の役割を担っていました。閉山したのち、国の重要文化財と史跡に指定され、現存する施設や機械は、今も大切に保存されています。
現地の専門ガイドの方の説明を聞きながら、万田坑にそびえたつ第二竪坑櫓や、レンガ造りの重厚な建物、炭鉱マンたちが行き来した坑口、巨大な巻揚機が残された機械室など、実際に見ると迫力満点で、当時の様子を思い描き、感心するばかりでした。
万田坑の入り口には、平成21年4月にオープンした「万田坑ステーション」があり、たくさんの資料や写真が展示され、炭鉱マンや技術者たちがともにした苦労や喜びを今に伝えています。
荒尾市には今回の万田坑のほか、ラムサール条約湿地に登録された荒尾干潟があり、同日もたくさんの見学の方が来られていました。佐賀市にも同じく世界文化遺産の「三重津海軍所跡」とラムサール条約湿地の「東よか干潟」があり、同じような条件の中、地域活性などにどのように活用されているかも興味深いものがありました。




次に、長洲港から有明フェリーで多比良港へ渡り、島原城見学と、武家屋敷の散策へ行きました。
島原城は、城内をめぐる資料館になっていて、当時の甲冑や刀剣の展示も抱負で、キリシタン迫害の歴史が分かる展示もありました。最上階からの海と山の眺望はとても素晴らしかったです。
武家屋敷の散策の道中、帰宅中の小学生から元気な声で挨拶をされて、こちらが元気をもらいました。


2日目は、長崎県長崎市にある「三菱重工長崎造船所史料館」へ。
長崎造船所内には「第三船渠」「占勝閣」「旧木型場」「ジャイアント・カンチレバークレーン」の4つの構成資産があります。
その中で、一般公開されているのが「旧木型場」長崎造船所に現存する最も古い建造物で、木骨煉瓦造二階建、明治31年に鋳物製品の需要増大に対応して建設されました。昭和60年に今回視察した「造船所史料館」として改装され、日本最古の工作機械や、造船所の歴史を紹介する展示施設となっています。
施設内では、DVD上映により長崎造船所の歴史について学び、その後館内の貴重な資料や、実際に使用されていた機械、船の模型を数多く見る事ができ、改めて当時の日本の技術の高さに驚くばかりでした。
史料館として改修された旧木型場の赤煉瓦は、昭和20年8月の空襲や原子爆弾の爆風にも耐えており、現存するその外観を見るだけでも価値のあるものでした。


今回の視察では、フェリーでの移動や散策、視察の合間を縫って、各自治会の情報交換や親睦を深め、お互いの自治会の問題点を理解するなどの時間もあり、とても充実した視察研修となりました。